随園食単
『随園食単』は
袁枚(1716年~1797年)は字は子才、号を簡斎、別の号として随園である。袁枚は1739年に24歳で科挙で進士科に及第したエリートであったが、優遇されず地方を転々とし、父親が亡くなった後に1749年の春に33歳( ※ウィキペディア等の他の資料では38歳と記載されている )で官職を辞し隠居生活に入ってしまう。
辞職後、南京の城西にあった
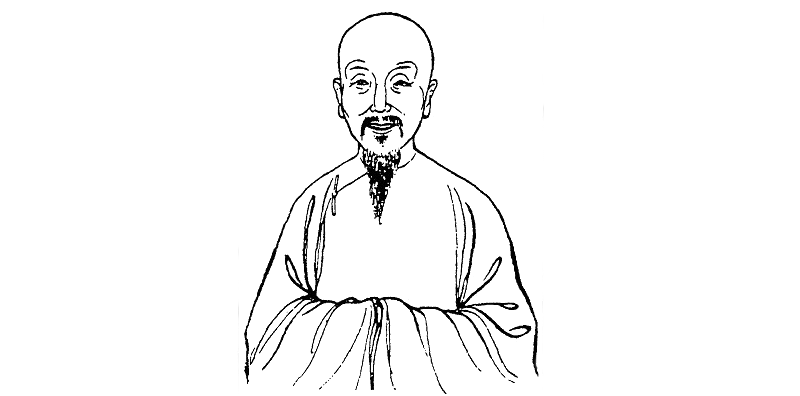 袁枚 肖像
袁枚 肖像
袁枚は、その生涯で30余種の著書を残したが、『随園食単』は1792年(乾隆57年)に刊行されたということなので、袁枚が76歳頃の著作という事になる。( ※ ちなみにブリア・サヴァランの『美味礼讃』が刊行されたのは70歳の時、1825年の死の2ヶ月前である )
『随園食単』の内容は、味つけや取り合わせを知ることなどの予備知識について20項、材料の浪費や味の混濁を戒める警戒事項14項を述べてから、海産物9項、川魚6項、豚肉43項、獣類16項、鳥類47項、有鱗水族17項、無鱗水族26項、精進47項、小菜43項、点心55項、飯粥2項、茶酒16項の、料飲について作り方、飲み方についての説明を記載している。40年をかけてこれらを招待を受けた先の主人や料理人たちから収集して編著したものである。
料理哲学に関して
『随園食単』第一巻の「須知單」にある先天須知で、まずは知っておくべき事として「天の与えた性質を知ること」を説いている。その中で、司廚之功居其六,買辦之功居其四と述べ、料理の素材が悪ければ、料理人が調理しても駄目であり、美食の功績は、料理人が6割、素材の購入4割であるとしている。これは『美味求真』でも強調されており、木下謙次郎も『随園食単』にその料理哲学の多くの部分を負っていると言えるだろう。
また『美味求真』では本味を濫りに用いるべきではないと強調しているが、『随園食単』でも先と同じく第一巻の「須知單」に變換須知という項が設けられていて、一物有一物之味,不可混而同之と述べて様々な素材の本味を混ぜて調理することを戒めている。この点も木下謙次郎が『随園食単』から引用し、かつ指摘する大きな要素となっている。
これらの料理哲学は不変のものであり、現代においてもその方向性は何ら変わるものではない。
『随園食単』では禁止事項として「
例えばさもしいレストランではキャビアとフォアグラとトリュフといった高級食材をやたらと使おうとしたり、しかもあろうことか、これらの食材を組み合わせて出してきたりする場合がある。また旅行で内陸地にある宿に行っても何故か食事に伊勢海老を入れて出して来るような所もある。これらは高級食材で豪華さを演出しようという耳餐としての行為に他ならない。もてなす側はこれを行うべきでは無いし、食べる側もそれを有り難がるのようでは味を理解しているとは言い難いのである。
このように食材の向き不向きや、なぜそれをここで食べるのかを理解せずに、こうした食材を濫りに用いることは避けなければならない事である。
さらに確かに珍しい食材は美味で価値があるものであるが、それを混濁して用いるのは、耳餐という過ちだけでなく、本味を濫りに乱用するという間違いまで犯してしまっている事を理解していなければならない。またこうした高級食材が入っているだけでそれを有り難がるのも耳餐に値すると言えるだろう。例えばキャビアはパーティーの席などでフィンガーフードにほんの数粒、申し訳程度にふりかけてあったりするが、それが何ら味に効果がある訳では無いし、しかもその品質は大体は最低のものである。悲しいかなキャビアが使われているという事だけが重要であり、その味はまったく顧みられていないのは嘆かわしいばかりである。
目食を有り難がるひとの食事に関して言えば、これはもうお子様ランチと同じであるとしか言いようがない。料理の品数が多いからと言ってそれが美味と直結している訳ではないのに、料理を数多く並べることに豪華さを感じる人は多い。
我々日本人は目でも食べるといって、盛り付けの美しさも重視するが、これは目食を意味するものでは無い。盛り付けによって食材の味そのものが際立たせられていれば、それは良いのである。ただ過剰な装飾によって、味では無く、豪華さだけが演出されているような料理は目食であると言わざるを得ないであろう。
そんなに一度に食べれもしないのにテーブルの上にやたらを料理を持ってきて並べられることがある。そうなると先に出てきた料理は冷えてしまい、刺身は乾燥して表面には潤いがなくなってしまう。味を損なうだけでなく、料理を出す順番から生じる味の演出も、調和も無く、まさに食い散らかすと表現するしかない様子の食卓となってしまうのである。
たまに「貧乏くさい料理」というような料理に優劣をつけるような表現をする人があるが、貧乏くさいのは自分の料理に対する感性の方であって料理ではない。豪華な料理よりも、むしろメザシの一本に真味が潜んでいることもあれば、里芋の土のミネラル感の高さにこそ旨さの真髄が溢れていることもある。これらを理解もしないで料理の云々を語る者こそが大概に耳餐目食の誤りに落ち込んでしまっているのである。これを『随園食単』は戒めており『美味求真』もまた同様にこうした行為を避けるように戒めている。
翻訳本に関して
『随園食単』は青木
『随園食単・訳余贅語』を見ると、青木正児は当初、随園ではなく、清の顧清仲『養小録』の気取りのなさを好んだ事が述べられている。また『随園食単』を翻訳することになったいきさつとして「戰時中食糧難から食物の話に興味が向つて」と理由を述べており、この翻訳は誰もが空腹であった時代を背景として翻訳されたものであったという事が伺える。その精神を感じるならば、『随園食単』を下敷きにして単に飽食や料理の豪華さを物質的に語ったり、あるいは追及することには間違っているような気がするのである。むしろ埋められないものを空想やイマジネーションによって補完するような精神的なものこそが、「食」そのものの本質に到達するための方法であるように思われるのである。それは例えばバタイユのエロティシズムのような「性」にも底通していて、これらは実は同じ方向線上にあるものではないかと考えている。
 青木
青木青木正児は戦中のナショナリズムの台頭してい時代、国粋主義が幅を利かせたであろうその中で、中国文学の研究を行っていた。また食料が十分になく、人々が飢えていた時代に『随園食単』のような現代の我々にとってグルメ本として捉えられているような書籍の翻訳を進めていた。こうした時代の背景を考えても、その当時の青木正児は、まさに二重の意味で孤高の存在であったとしか言いようがない。
青木正児の後半生を特徴付ける学問に名物学が挙げられる。この「名物学」とは特産品についての学問だと思われてしまうこともあるかもしれないが、実際は名物学とは「名」と「物」の対応関係を調べる学問である。つまり名物学は、ある時代のある場所で使われている名前は現在の何を指しているのかということを明らかにする学問である。
青木正児は名物学のベースとして10冊のノートを残している。『鄙事備忘』『竹窓雑鈔』の1と2、『鴻城雑録』、『鼓東雑録』、『借読鈔存』2~6である。これらは名物学に関する内容が大半を占めているが、とりわけ飲食関係の内容が目立ち、その内訳は次のようになっている。
①菓子関係、②料理関係、③酒関係、④茶関係、⑤その他
こうした名物学における名前と物との関係、特に飲食に関してその関係性を明らかにすることに精通していたことは、青木正児の翻訳した『随園食単」に成果が如実に表れている。なぜなら食材はともかく、料理の名前や調味料の名前は長い年月を経てその名前が変わったり、失われたりする事が多いものだからである。それを補い註釈を付するという点で名物学は『随園食単」の翻訳に大きく貢献したはずである。
例えば『随園食単』の五:猪肉の部(30)醤肉の注(1)には、
「明代の『居家必用事類全集』には醤の作り方は種々有るが、『麪醤』は白麪(うどん粉)を材料にしたものである」と註釈されている。一方、青木ノートの『借読鈔存』(六)にも『居家必用事類全集』の「諸醤類 造肉醤法」の条項があり、こうした知識の蓄積が『随園食単』の翻訳にクロスオーバーに反映されていることが理解出来る。
また青木正児の著書には『抱樽酒話』『酒の肴』『華国風味』といった食に関する書籍もあり、戦後の物資不足のなかで書かれたとされるこれらの書籍からも、疑いのない青木正児の食に関する造詣の深さを伺い知ることが出来る。『随園食単』はそれだけでも非常な名著であるが、青木正児という博学な人物によって翻訳が行われたことで、更なる決して避けて通れない美食における必読の書となっているのである。
追記
フランス文学者の澁澤龍彦は『華やかな食物誌』で『随園食単』について書いており、そこでは青木正児の註についてもふれている。その中でも澁澤龍彦が「果子狸」に関して言及している部分があるので注意を引いておきたい。
まずは『随園食単』の「果子狸」に関する部分を引用する。
【 隨縁食単:果子狸 】
果子狸鮮者難得。其醃乾者,用蜜酒釀蒸熟,快刀切片上桌。先用米泔水泡一日,去盡鹽穢。較火腿覺嫩而肥。
【 青木正児 訳 】
果子狸の鮮は得難い。その塩乾したものは密と酒娘で蒸熟して、快刀で片に切って卓に上げます。まず米のとぎ汁に一日浸しおき、塩をぬき尽くす。火腿に比べると柔らかで脂こい。
と記し、その後に註釈として「果子狸」一名玉面狸。狸の一種で、常に樹に登って果実を食うと説明してある。つまり狸の種類であるという説明になっているのである。
それに対して澁澤龍彦は次のように記してある。
【 華やかな食物誌 】p88
「獣類の部」に果子狸と称する、おそらく中国南部の山地に棲む麝香猫かと思われる獣のことが出てくる。青木正児は狸の一種と見ているようだが、むしろこれは麝香猫のほうが正しいのではないだろうか。
この箇所が気になってはいたが、澁澤龍彦はここでその出典根拠を特に示しておらず、しかも青木正児は中国文学における「名物学」の権威であるので、当然、澁澤龍彦の方の間違いだろうぐらいにしか思っていなかった。しかし、よくよく調べてみると澁澤龍彦の方が正しいことがはっきりした。果子狸とは狸の種類ではなく、ジャコウネコ(ハクビシン)の種類である。(学名:Paguma larvata - 食肉目ジャコウネコ科ハクビシン属)
実は澁澤龍彦の本を読んでいると、これは間違いっているだろうと思って、裏取りで調べてみると、逆に澁澤龍彦の方が正確である事が何度もある。その度に、澁澤龍彦の博学さと、その文章の背後にある、膨大な資料に当たり、出典元もしっかり調べたうえで書いているという事につくづく感心させられるのである。澁澤龍彦、やはり流石である。
さて話を戻して青木正児である。この箇所は麝香猫が正解であるが、註釈ではさらに果子狸に関して「浙江に産し、糟漬けにして珍品となす。酒の酔いを醒ます効果があるという」と述べて、さらに深いマニアックな註釈を挿入している。これもまた、私が青木正児の博学さに感心させられて止まない要因である。
参考資料
「正統性はいかに造られたか ― 蘇州における袁枚の社会的威信の伸展 ―」 王 標 - 都市文化研究 Studies in Urban Cultures Vol.5, pp. 46-61頁,2005
「随園詩話の世界」 : 松村 昂 - 中國文學報 (1968), 22: 57-99
「青木正児とその名物学研究」 : 辜承尭
「 青木正児の名物学研究とその評価について」 : 辜承尭