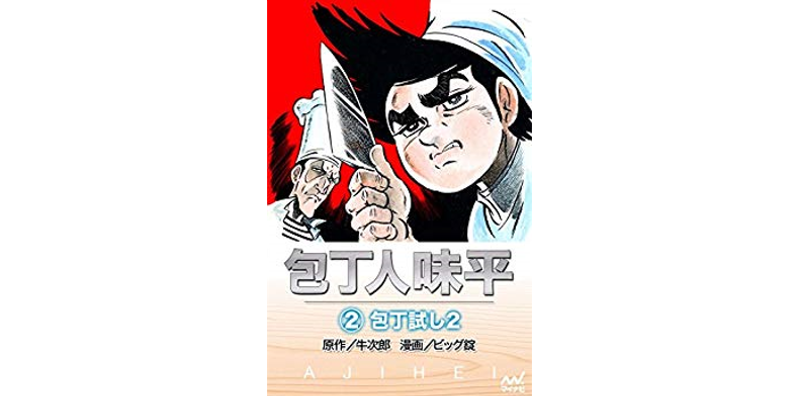磐鹿六雁命
日本料理の神様
『日本書紀』によると、磐鹿六雁命は、景行天皇の東国巡幸の際に白蛤を膾にして献上したところ大変に気に入られ、お褒めの言葉を賜ったとある。献上された膾の料理とは、ハマグリを包丁で細切りしたもので、いわゆる刺身のようなものと考えて頂ければ良いだろう。こうした功績の故に、磐鹿六雁命とその子孫は天皇の食事への奉仕を任されるようになったとある。
またその際に、膳臣(かしわでのおみ)の姓を賜り、さらに膳大伴部(かしわでのともべ)という、朝廷における料理のための集団を統括する役割も与えられている。
昔、膳は「かしわで」と読まれていた。その理由は、食物は「柏の葉」などの木の葉に盛られて供されていたからである。つまり膳(かしわで)は食器の一種で、直接食物を乗せるものを意味していたのである。磐鹿六雁命には、料理を司るという任務が与えられたので、そこから膳臣(かしわでのおみ)の姓が与えられたと考えられる。
こうした古の事績を踏まえて、やがて磐鹿六雁命は日本料理の神様とみなされるようになっていった。現在では高家神社(千葉県南房総市)、高椅神社(栃木県小山市)、高橋神社(奈良県奈良市)で、磐鹿六雁命は料理の神として祀られている。また特に日本料理人の中には、磐鹿六雁命を料理の神様として敬意を払い、祀り続ける者が少なくない。
『新撰姓氏録考証 第二巻』から磐鹿六雁命の家系を見ると、曽祖父が第8代の孝元天皇、祖父はその皇子の大彦命、父親は比古伊那許志別命(大稲腰命)とあり、磐鹿六雁命は天皇家に繋がる家系の出であったことが分かる。
後代になると、その子孫は、膳氏あるいは高橋氏という姓名を名乗るようになり、明治時代になるまで、かなりの長期間にわたり天皇の料理を作る職を世襲によって務め続けた一族となってゆく。
この子孫については高橋朝臣の項で詳しく説明を加えることとしたい。
『日本書紀』の磐鹿六雁命
『日本書紀』の景行天皇に関する記録のなかには、磐鹿六雁命についてのエピソードが次のように記録されている。
【 日本書記 】
冬十月、至上總國、從海路渡淡水門。是時、聞覺賀鳥之聲、欲見其鳥形、尋而出海中、仍得白蛤。於是、膳臣遠祖名磐鹿六鴈、以蒲爲手繦、白蛤爲膾而進之。故、美六鴈臣之功而賜膳大伴部。
【 現代訳 】
冬十月に、上総国(千葉県)に到着し、海路によって淡水門をお渡りになられた。この時、覚賀鳥の声が聞こえ、その鳥をご覧になろうと海の中に出ていかれた。そこでハマグリが取れたのである。
すると膳臣の遠い祖先にあたる磐鹿六雁が、蒲の葉で襷(たすき)にして、ハマグリを刺身にして天皇に献上した。ゆえに天皇は磐鹿六雁の功績を褒めになり、膳大伴部を賜えられた。
磐鹿六雁命は景行天皇にハマグリの膾を献上し、それを景行天皇がお褒めになり、膳大伴部(かしわでのともべ)の立場を賜わったとある。
『高橋氏文 』の磐鹿六雁命
『高橋氏文』には、『日本書紀』とほぼ同じような内容が記載されている。
この『高橋氏文』は、磐鹿六雁命の子孫である高橋氏に伝わっていたとされる私文書なのであるが、完本は現存しておらず、逸文だけが『本朝月令』,『政事要略』,『年中行事秘抄』に断片的に残されているので、現代の我々はそこから内容を理解できるようになっている。『日本書紀』と対比するため、長文だが重要なので『高橋氏文』を以下に引用しておく。
【 高橋氏文 】本朝月令 六月朔日 内膳司
口に出すのも恐れ多い巻向日代宮(まきむくのひしろのみや)で天下をお治めになった景行天皇の治世五十三年八月、天皇は群卿たちに詔して仰せられた。
「私が愛しい子を思うことは、いつになったらやむであろうか。小碓王(おうすのみこ)[またの名を
天皇は
このとき、大后が磐鹿六獦命に仰せられた。
「この浦で、霊妙な鳥の鳴き声が聞こえた。それは、“ガクガク”と鳴いていた。その姿を見たいと思う」
そのため、磐鹿六獦命が船に乗って鳥のところまで行くと、鳥は驚き、他の浦へ飛んでいった。なおも追いかけて行ったが、ついに捕らえることはできなかった。そこで、磐鹿六獦命は呪いをかけていった。
「鳥よ、お前の声を慕って姿を見たいと思ったのに、他の浦に飛び移って姿を見せなかった。今から以後、陸に上がってはならぬ。もし陸に降りることがあるならば、必ず死ぬぞ。海中を住処とせよ」
帰るとき、船の艫のほうを振り返って見ると、魚がたくさん追いかけてきた。そこで、磐鹿六獦命が角弭の弓を泳ぐ魚たちのなかに入れると、魚が弭にかかってきて、たちまちたくさんの魚を獲ることができた。そこで、その魚を名づけて、“頑魚(かたうお)”と呼んだ。これを今の言葉で“カツオ”という。[今、角を釣り針の柄をにしてカツオを釣るのは、これに由来する]
船は潮が引くことに遭って渚の上に乗り上げ、動けなくなった。船を掘り出そうとすると、大きな白い蛤がひとつ出てきた。磐鹿六獦命は、カツオと蛤の二種類の品物を捧げて、大后に献上した。
すると大后は、そのことをお誉めになりお喜びになって仰せられた。
「それをおいしく美しく料理して、天皇のお食事に差し上げなさい」
そのとき、磐鹿六獦命は、「六獦が料理をさせて奉りましょう」と申し上げ、
このとき、天皇が仰せになるには、「これは、誰が料理して進上したものか」とお尋ねになった。そこで、大后が申し上げた。
「これは磐鹿六獦命が献上したものです」
すると天皇はお喜びになり、お褒めになって仰せになられた。
「これは、磐鹿六獦命一人の力で行ったことではない。天にいらっしゃる神が行われたものである。大和の国は、行う仕事によって名をつける国である。磐鹿六獦命は、我が皇子たちに、また生まれ継ぐ我が子々孫々までに、永遠に長く、天皇の食事に関わる職掌に清め慎んで従事し、仕え申しあげよ」と、
また、「この仕事は、多くの伴が立ち並んで奉仕するものとせよ」と仰せになり、東西南北の諸国から人を割き移して、大伴部と名づけ、磐鹿六獦命へお与えになった。
また、諸氏の氏人や東方諸国の国造十七氏の童子を、それぞれ一人づつ献上させ、平坏と領布をお与えになって、彼らの統括を委ねられた。「山野海河は、ヒキガエルの渡る果てまで、船の通う果てまで、海の大小の魚、山のさまざまの獣など、お供えするすべてのものを統括し取り仕切って奉仕せよ」と任じられた。
「このように委ね任じることは、私ひとりだけの意思ではない。これは、天にいらっしゃる神のご命令であるぞ。我が王子・磐鹿六獦命よ、諸々の伴たちを督励し統率して慎み勤めて奉仕せよ」と仰せられ、祈誓されて委ね任じられたのである。
このとき、上総国の安房大神を御食つ神としてお祀りして、若湯坐連らの始祖・意富売布連の子の
『高橋氏文』を読むと基本的には『日本書紀』と同じ内容であることが分かる。しかし、細部をみると『高橋氏文』の方がより詳しくこの出来事について語られていて、『日本書紀』にはない情報も多く含まれている。
その情報の相違点として最も重視するべきなのは、『日本書紀』は白蛤を膾にして天皇に献上したのに対し、『高橋氏文』では「白蛤」と「鰹」で、膾をつくり、煮炊きして、さまざまに料理し盛りつけて献上したというところである。これはささいな違いでしかないように思われるかもしれないが、日本料理がどのように作られていったかという本質の部分について考えると、非常に重要な意味がこの記述に孕んでいるように私には思えるのである。
なぜ『高橋氏文』には、鰹の膾が付け加えられているのか。それを理解するためには、『高橋氏文』が、その当時に、そのような背景のものとで提出されたのかをまず知る必要があるだろう。
『高橋氏文 』の背景
奈良時代には中国(唐)から律令制度が取り入れられ、大和朝廷は唐に習った官制制度の元で組織作りが進められた。この官制組織は天皇の料理を司る厨房組織においても例外なく適応されている。なぜなら中国では紀元前の周の時代から、厨房組織が政治組織と並行して組まれるほど重要視されており、宰相がトップとして厨房組織を司さどらなければならないとされているほど重要なものと見なされていたからである。
中国では『周礼』にあるように、紀元前の周の時代から厨房組織が政治組織と並行して組まれるほど重要視されており、天官家宰(宰相として国を治める者)が飲食調理のことも司らなければならないほど、厨房組織というものは重要であるとされていたのである。
日本では西暦701年に大宝律令が施行された。それ以来、大陸(唐)に習って官僚組織が組織化され、当然、天皇の厨房組織も律令制度のなかに組み込まれて組織化されることになった。その時の厨房組織は以下に示すように、大きく内膳司と大膳司に二つに分けられ、さらにその中に各部門が並ぶという構成になった。
別当:他の官司の職務全体を統括・監督する地位に就いた時に補任される地位。
奉膳:内膳司の長官に相当する。定員二名。主に高橋・安曇の両氏が長官職を担当した。
典膳:内膳司の次官に相当。定員六名。
令史:内膳司の 主典に相当。定員一名。
膳部:内膳司の職員。定員四十名。調理役。
造餅長:製餅調理員。
作木器:木器製作員。定員は二人。
作土器:土器製作員。定員は九人。
五畿内諸国の
大膳大夫:定員は一人。正規定員外の権大夫が一人いた。
大膳亮:定員は一人。正規定員外の権亮が一人いた。
大膳大進:一名
大膳少進:一名
大膳大属:一名
大膳少属:一名
主醤(ひしおのつかさ):二名
主果餅(くだもののつかさ):二名
史生(ししょう)
職掌(しょくしょう)
使部:三十名
直丁:二名
駈使部:八十名
率分勾当:諸国からの調を別に分けて収納する役。
主菓餅:定員は二人。菓・餅をつかさどった役。
主醤:定員は二人。醤をつかさどった役。
他に、鵜飼・江人・網引・未醤戸などの雑供戸があった。
高橋氏は「
【 補足説明 】
天皇の行う最も重要な祭祀は「大嘗祭」である。これは天皇が即位して最初に行う新嘗祭であり、即位中で1回だけ行われる。
天永2年(1111年)まで書き続けられたとされている『江家次第』によると、「鮑汁漬」は高橋氏、「海藻汁漬」は安曇氏の担当であったことが記載されている。
また大正天皇の大嘗祭の後の大正4(1915年)に発刊された『御即位及大嘗祭』に記載されている大嘗祭神饌の内訳を確認すると、しっかりと「鮑汁漬」と「海藻汁漬」が含まれていことが分かる。よってこの二品は1000年以上を経た現代の大嘗祭神饌においても祭祀で用い続けられているのである。
さて、祭祀における並びは、先に高橋氏、その後に安曇氏という順番が長らく守られていた。しかしこの並び方に関する論争が、大宝律令が定められてから約15年後に勃発することになる。この辺りの経緯は、江戸時代後期の国学者だった伴信友が、『高橋氏文考注』で注釈を加えながら述べているので、以下にその内容をまとめて説明しておくことにしたい。
① 霊亀二年 十二月(西暦716年)
安曇宿禰刀が、「祭礼の儀式において高橋氏が先に並び、安曇氏がその後に並ぶのは受け入れられない」と意義を唱え始めた。これに対して高橋朝臣平具須比は、「神事の際に御膳に仕えることが出来るのは高橋氏だけであり、そもそも安曇氏がこれに参加することが間違えている」と反論。この時は天皇が仲裁役となり、高橋氏が前を、その後に安曇氏が続くのが正しいと『累世神事』の記述を根拠に論争を収めている。
② 宝亀六年 六月(西暦775年)
この論争が勃発して60年後、神事の際に安曇宿禰広吉が、前に並ぶ高橋波麻呂を無理やり押しのけて前に割り込みを行った。一方、割り込まれた高橋波麻呂は、高橋氏だけが御食を捧げるべきであるとして、安曇宿禰広吉を列から引きずり出すといういざこざを起こしている。
この事件に対して両氏には罰が与えられることになったが、高橋氏は自分には咎がないことを天皇に対して主張し、それが認められた為、安曇氏だけが重い罰を受けることになった。
こうした待遇に不満をもった安曇宿禰広吉は、高橋氏よりも優位になる為に、安曇氏の氏文(氏族の記録文書)に改竄を行うことで対抗する。高橋氏は先に述べたように、その先祖である磐鹿六雁命の時代から景行天皇の代から仕え始めたという記録があるが、それに対抗して安曇氏は、高橋氏よりも二代も古い崇仁天皇の代から仕え始めたとする説を氏文に書き加えたのである。( ※ 日本書紀によると、実際に安曇氏は応神天皇の代から仕え始めており、高橋氏の仕えた景行天皇よりも四代後から天皇に仕えていたことになっている。 )
しかしこの改竄は成功し、安曇氏が、高橋氏の前に並ぶのは歴史的に正しい根拠があるとみなされるようになる。そのため高橋氏はそれに従わざるを得ず、これ以降、祭祀の並びがまずは安曇氏、そして高橋氏はその後ろに並ぶことになった。
③ 延暦八年(西暦789年)
その後も、高橋・安曇の両家の論争は続いたため、その正当性を確認するため、朝廷は、高橋氏および安曇氏の両家に氏文の提出を要請。この際に、高橋氏側から出されることになった文書こそが『高橋氏文』なのである。
④ 延暦十一年(西暦792年)
提出から三年後、太政官が安曇氏の提出した氏文は、改竄されたものであることを指摘。よって高橋氏の起源こそが正しく、安曇氏の起源には偽りがあるとした。しかし桓武天皇はこの件に関して『累世神事』を根拠に、高橋氏と同様に、やはり安曇氏も神事を行う正当な家系であるのは間違いないとして、二氏の間で一回づつ前後を入れ替えて並ぶという妥協案を提案して仲裁を行なおうとしたのである。
しかし、この方法に安曇宿禰継成は納得せず、6月、12月の
『高橋氏文 』が主張すること
高橋氏と安曇氏の間の確執の最中に、それぞれの氏文が提出されたことを考えると、各々の氏文に込められた意図がどのようなものであるかが透けて見えてくる。当然、朝廷に提出する文書は、自分たちの正当性や、より優位性を際立たせる為のものであり、氏文はその根拠として重視されたと考えられる。
ゆえに安曇氏は、氏文に意図的な改竄までも行って、高橋氏よりもより有利なポジションを得ようとしたのだが、結果的に、太政官によって改竄は発覚することになってしまった。
一方の高橋氏も、安曇氏と同様の意図をもって『高橋氏文』を提出したはずであり、より有利なポジションを得るために何らかの改竄・あるいは修正を加えた上で文書を提出した可能性は十分に考えられる。
例えば『高橋氏文』の逸文(断片)は、『政事要略』の中にもあって、それは以下のような内容となっている。
【 政事要略 】
六雁命は、景行七十二年八月に病に冒され、同じ月に亡くなった。天皇はそれをお聞きになって大変悲しまれた。そして親王の方式に従って葬儀を行うことをお許しになり、宣命使として、藤河別命、武男心命らをお遣わしになった。
宣命として云うには「天皇のお言葉として仰せになるには、王子の六雁命が思いがけなく亡くなったとお聞きになられて、一日中悲しみ憂いておられる。天皇の治世の間は、六雁命も健在であり、お互いに顔を合わせていられるだろうとお思いになっているうちに、別れが訪れてしまった。そこで、今お考えになることは、十一月の新嘗祭のことも、膳職が御膳に奉仕することも、みな六雁命が苦労して創始したものである。これによって、六雁命の御魂を膳職で斎き奉り、将来にわたって永く奉仕させることにしよう。
六雁命の子孫たちを、未来にわたって膳職の長官、上総国の長官、淡路国の長官に定めて、その地位に他の氏の者を任命されることはせず治めさせよう。もし、膳臣の一族が継がないときには、我が王子たちを任じ、他氏を加えて混乱させることはすまい。
若狭の国は、六雁命に永く子孫たちの永遠の所領とせよと定めてお与えになられた。このことは、後世にも決して違反しない。この志をわきまえ、よく膳職の内も外も守護し、歴代の天皇には宮の災いのことなどもなく、過ごして頂きたいとお考えになっている、と仰せになった天皇のお言葉を、六雁命の御魂も聞き届けよ」と仰られた。
上記はリンク先の『政事要略』の写本をもとにして、それを口語訳にしたものである。ここでは磐鹿六雁命の死後、その子孫を上総の国、および淡路国(安房国)の長官とし、また若狭も磐鹿六雁命の子孫が引き継ぐ永遠の所領として定められた述べられている。
上総の国は現在の千葉県であり、景行天皇の東国巡幸の時に、磐鹿六雁命が料理をしたゆかりの地であるので、その地の長官とされるのにはもっともな理由があっただろう。
それに対して若狭国が所領とされてことには歴史的な謂れがなく、唐突に若狭国との関係が書かれているように感じられる。このような突然に若狭国が出てきた理由は、磐鹿六雁命から数世紀も時代を経た後になって、高橋氏が若狭の長官職(国守)を務めるようになったことに起因しているように思われる。つまり『高橋氏文』逸文に「若狭を所領した」とあるのは、こうした事実に基づいて後から付け加えられたものであろう。
律令制成立以前の6世紀頃から高橋氏は若狭国において影響力のある存在であった。律令制成立(8世紀)以後は、若狭国に、内膳司である高橋人足、高橋子老、高橋安雄の3名が国守に任命されているほどなので、若狭国は高橋氏が強い影響力を持っていた地域であることは間違いないだろう。よって若狭の国における所領の正当性を示すという意味においても、その地が景行天皇によって磐鹿六雁命の子孫に委ねたものであるということを『高橋氏文』のなかで述べておく必要があったのだと推測できる。
磐鹿六雁命が、景行天皇にハマグリの膾を献上した出来事は何年ぐらいだったのかについて年代的に正確なことは分かっていない。ただ歴史的な流れで概観してみると、西暦3〜4世紀頃の出来事であったのではないかとは考えられているようである。『高橋氏文』は、その時代から高橋氏に残された文書であったというよりは、その内容から鑑みると、論争が起きた正に8世紀になってから書かれた文書であるとする方が理にかなっているようである。
安曇氏との争いの故に、朝廷に『高橋氏文』を提出したのが、8世紀後半の延暦八年(西暦789年)であったことを考えると、高橋氏の正当性の根拠とされた『高橋氏文』は歴史的に深い根拠に基づくものでは無かったようにも思える。むしろ、安曇氏との争いのさなかに作意的につくられた、あるいは書き換えられた文書が『高橋氏文』であり、そこには自分の氏族が有利になるような何らかの記述が意図的に含まれたと考えたほうが筋が通るように思える。
磐鹿六雁命の料理
『高橋氏文』で、特に注視したいのが『日本書紀』には記述がなく、『高橋氏文』だけにある、磐鹿六雁命が鰹(かつお)を膾にし、料理して天皇に献上したという記述である。なぜ『日本書紀』には白ハマグリを膾にして出したという記述しかないのに、『高橋氏文』には、それに加えて鰹を料理したとあるのだろうか。
この理由を検討するにあたり、まずは日本料理の「割主烹従」がいつ始まったのかという事を理解する必要があると私は考えている。なぜならば「割主烹従」とは日本料理特有の考え方であり、それが日本料理の厨房組織を特殊なものにしているその根本に存在するものだからである。では「割主烹従」とは何を意味し、それがどのように日本料理における特徴になっているのか、さらにはそれがいつから始まったのかを説明しておきたい。
割主烹従と日本料理
まずは「割主烹従」という言葉の意味から考えてみたい。
日本料理でいう「割主烹従」とは文字通り、割く(切る)ことが主で、烹る(火を使う)ことが従であるという考え方である。よって日本料理の厨房組織もそれに沿っており、厨房にはトップである
次の位に
さらにその下には
このように「切ること」を非常に重視する日本料理の厨房組織の根底には、
また日本料理が、あくまでも「割く(切る)」ことこそが重要な料理であると見なしていることは、料理人や料理長を、板前、花板、次板、脇板のように、割くのに必要な俎板と関連付けた呼称がそれぞれ付けられていることからも理解できる。
こうした割主烹従の考え方を基盤とした日本の厨房組織の構成は、非常に特徴的である。なぜなら調理場における職務内容(割くこと、あるいは烹ること)とその地位がシンクロしているからである。日本料理のこうした厨房組織のヒエラルキーは、やはり「割く(切る)」ことが最も重要な要素であることを意味するものであるが、このような要素に基づく厨房組織の構成は西洋料理の世界には存在しないものである。割くこと、つまり切ることに対するその高い優位性と位置付けは、他国の料理文化に見られないのである。
日本料理の厨房組織に対して、西洋および中国料理の厨房組織は、よりフラットな構造になっており、そこには「割く(切る)」ことに対する優位性のようなものは存在していない。
その組織の違いを、フランス料理であるならばベルサイユ宮殿の厨房組織について記したイポリーヌ・テーヌの項から。さらにはオーギュスト・エスコフィエの「ブリゲード・ド・キュイジーヌ」(仏:Brigade de cuisine、“料理の旅団”)という組織編成、あるいは『周礼』にある中国料理の厨房組織については、「包丁人」の項で詳しく説明を加えているので、日本料理の厨房組織と比較して頂きたい。
私はこれらを比較して、どちらが優れているとか、劣っているかを論じようとするつもりはない。ここで指摘しようとする私の関心事は、こうした組織形態の相違の根本には一体何があるのかということをまずは明らかにしておきたいだけなのである。
日本料理における厨房の組織形態をみると、あくまでも「割く(切る)」ことを重要視するあまり「割く(切る)」という料理工程を中心にして階層化された厨房組織として形成されてきたと考えられる。つまり「割く(切る)」という行為をより高め、それを神格化するために、このような独自のヒエラルキーが日本料理界には形成されてきたという仮説が成り立つ訳である。こうしたヒエラルキーが生まれ、長年に渡って支えられてきたその核には何があったのだろうか。
割主烹従 の背後にあるもの
割主烹従という考え方によって、つまり調理工程によってそのヒエラルキーが形成されている厨房組織は、先に述べたように日本だけである。実はこうした組織のありかたや、それを支える権威と結びついた影響力は、庖丁流派によって形成されてきたものであると、木下謙次郎は『美味求真』の中で述べている。確かに、割主烹従という考え方は、庖丁流派によって守り伝えられ、文化や伝統さらには組合組織を通して日本料理のおける価値観の形成されたと言えるだろう。そしてそうした伝統や歴史は、実際に内膳司として活躍したの高橋氏、およびその祖である、磐鹿六雁命を祀るコンサバティブな料理人組織によって長年に渡って守られてきたものであるとも言えよう。
好意的に考えるならば、こうした日本料理のスタイル(厨房組織においても)は世界と比べても個性的で、高いオリジナリティを有しているものと言えるかもしれない。しかし木下謙次郎は『美味求真』の中で、庖丁流派が重視してきたこうした日本料理の独自性と考えられているようなものの根幹は、形式や見た目だけを重視するの要素でしかないこと、またそれが本質的な至味の追及(求真)につながっていないことを指摘している。
その証拠に、日本の厨房組織形態は意図的に「味」を追求する組織ではなく、技術を、特に割くことを中心とした料理工程を追求する組織になっているからである。見た目の飾りや、そのための技術は必要な事であるかもしれないが、料理の本質において考えると、こうした技術的なことはすべて「味」に従属すべきであり、見た目に「味」が従属するような料理は、本来のあるべき料理の姿から逸脱していると言わざるを得ないからである。
日本料理の厨房組織の特徴を、日本特有の歴史的な伝統として重視すべきであると考える方もあることだろう。無論、私もそのことに異論を唱えるつもりは無い。こうした組織の在り方が「味」の追及も、おざなりにしていないのであれば、それは全く問題ないのである。ただし、伝統という観点のみから、これを妄信的に重視すべきであるとしているのであれば、ひとつ異論を唱えておきたい。
ただそれを理解して頂く前に、そもそも日本の厨房組織とはどのようなものであったか、さらに割くこことがなぜそこまで重要視されるようになったのかを知る必要がある。なぜなら、それを知らずして「割主烹従」がなぜ日本料理の根幹となっていったのかの本質を理解することは出来ないからである。
奈良・飛鳥時代の厨房組織
西暦701年に大宝律令が制定された際、その組織は大きく内膳司と外膳司に別れていた。この組織形態は先述したように、中国(唐)の官制にならったものであった。つまりその時代には割主烹従という概念はまったく存在していなかったのである。その組織構成をみると分かるが、中国古来の厨房組織を踏襲したもので、割くとか、煮るといった厨房における役割によって位に上下がある訳ではなかった。
そらから程なくして、奉膳職にあった二家の高橋氏と安曇氏の確執が始まり、両家からそれぞれ氏文を提出するように朝廷からの要請が行われる。そこで高橋氏が提出したのが、先ほどから何度も取り上げている『高橋氏文』である。この提出文書は、高橋氏にとっては何としても一族の正統性と、安曇氏に対する優位性を裏付る文書でなければならなかった。そのためには何としても一族の歴史を補強する必要があったであろうし、その為には、『高橋氏文』に対する修正・改竄、あるいは書き換えを行うことも厭わなかったのではないだろうか。
しかし、高橋氏はあからさまな仕方でそれを行うことは憚られた違いない。なぜならば『高橋氏文』を提出することになった経緯は、まずは安曇氏が自分たちの優位性を主張する為に朝廷に提出した改竄文書が、朝廷による精査によって偽造と発覚した為だったからである。つまり朝廷は両方の家伝書を付き合わせて、どちらの主張が正当なものかを判別する必要があったのである。その為に高橋氏は『高橋氏文』を提出する必要があり、その文書によって一族の歴史を主張することで、安曇氏の主張に打ち勝たなければならなかった。
こうした状況において、高橋氏は『高橋氏文』に対して、大筋は変えず目立たないながらも何らかの改竄、あるいは修正や加筆を加えたと思われる。
まず高橋氏は、彼らの先祖の磐鹿六雁命に当然注目した。磐鹿六雁命は『日本書紀』の中にも料理についての事績が含まれており、景行天皇から料理を司どるように任命された人物である。その子孫である高橋氏にとって、この事績を伝える文書こそが、高橋氏の優位性を裏付けるものとなったに違いない。
だが『日本書紀』では、磐鹿六雁命は白ハマグリを膾にしただけである。これを料理の神として磐鹿六雁命を担ぎ出そうとする高橋氏が、インパクトが弱いと感じたならばどうだろうか。『高橋氏文』には、磐鹿六雁命は白ハマグリと堅魚(カツオ)を膾にし、調理したと記してある。しかし正史である『日本書紀』には、カツオについて一切触れられていない。
だが子孫の高橋氏は『高橋氏文』において、『日本書紀』にはない、磐鹿六雁命が魚を割く技術をもっておりカツオを見事にさばいて、白ハマグリと共に天皇に献上したという内容を伝えたのである。つまり魚を捌いて刺身にして出すという行為を付け加えたということになる。こうした技術は料理調進としての役割を担うにふさわしい事績となったに違いない。よってその子孫である高橋氏は、奉膳として、さらには天皇の料理を準備するのにふさわしい一族であり、安曇氏よりも歴史ある料理における事績を有する者たちであるという評価を得たのである。
結果的には、安曇氏の自爆ようなかたちで失脚し、高橋氏が優位性を勝ち得た事になったが、これは単なる表面的な結果論であり、その過程においては、高橋氏、安曇氏ともに手段を選ばない正統性の主張があったものと思われる。その中で提出された『高橋氏文』は、歴史的な観点から見ると、やはり正確性が疑問視される文書として捉えられるべきであろう。
割主烹従の厨房組織への変化
さてここからが重要である。
『高橋氏文』によって磐鹿六雁命がさらに神格化されるようになると、律令制度のもとで定められた厨房組織における変化が生じるようになってゆく。磐鹿六雁命の事績から魚を捌く事、つまり割く事に対する行為そのものが重要視されるようになり、組織における割くことに対する地位が最も高いものになっていったのである。
平安時代になると、後代で言うところの庖丁人と呼ばれる者が現れるようになった。庖丁人とは庖丁式において、鶴や鯉を捌き、それを披露する者である。この技術は、ある種、上流階級の貴族のような人々の為の芸事、あるいは教養のようなものに組み込まれ、天皇の前や式典において披露されるものとなっていった。
庖丁人と、料理人の間には大きな乖離が生まれ、庖丁人は料理をする者ではなく、庖丁式を執り行い、そのための庖丁技術を有する者としてその存在が重要視された。それに対して料理人は実際に調理をし、料理を準備する者たちで、そこに庖丁人が上であり、料理人は下であるというヒエラルキーが生まれるようになっていたのである。
こうした構造は、料理人の中にも持ち込まれ、料理においては切る事・割く事こそが最も高い価値あることであるとされ、それが「割主烹従」という考え方につながっていったと考えられる。
割くことへの神聖化
こうした割主烹従におけるバックグラウンドを考えると、割くことに長じた人物がどのように神格化されていったかの過程が見えてくる。その始まりは磐鹿六雁命であり、正史の『日本書紀』にない、カツオの膾料理を調理したという事績の挿入は、正にその事を象徴的に表していると言えるだろう。磐鹿六雁命は包丁で捌くという事績によって神格化され、日本料理の神として祀られることによって日本料理人の信仰対象となったのである。
実は、歴史に登場する料理人は磐鹿六雁命が最初ではない。もっと以前に
【 日本書紀 】
天皇、則命吉備武彥與大伴武日連、令從日本武尊。亦以七掬脛爲膳夫。
【 訳文 】
天皇は、
ここでは七拳脛という人物が、料理人としてヤマトタケルの東征に同行したことが記されている。この出来事は景行天皇四十年の出来事であると記されているので、磐鹿六雁命のエピソードの13年前の出来事である。
つまり磐鹿六雁命よりもかなり前に七拳脛は料理人として景行天皇に認められており、それゆえにこそ景行天皇はヤマトタケルの東征に同行するように任じたのである。七拳脛という名前の意味は「スネの長さが拳で7つ分」ということである。よって七拳脛は足の長い人物であったのだろう。
さらにこの七拳脛につては、さらなる情報が『古事記』にも以下のように記されている。
【 古事記 】
凡此倭建命、平國廻行之時、久米直之祖・名七拳脛、恒爲膳夫、以從仕奉也。
【 訳文 】
ヤマトタケルの東征の時に、
『古事記』にも七拳脛が料理人であったという記述があるが、ここにはさらに『日本書紀』にはない情報として、七拳脛は、尾張国水上社の神官であった久米直の祖先であると述べている。
この久米氏の系図をみると、先祖には「天串津大来目(天津久米命)」であり、この人物はニニギの天孫降臨の際に先導役を務めた事が『日本書紀』には記されている。
また七拳脛の十代前の先祖には「大久米命」という人物がいるが、この人物は神武天皇の東遷に従って戦っている。この時に軍の士気を高めるために歌ったとされる「久米歌」は、この人物に由来したものである。
このように久米氏は、古来から天皇の護衛を行ったり、また軍隊を動かしたりする氏族であったようである。また後年、久米氏は神官にもなっているので、単に料理を作るだけではなく、七拳脛にはそれ以上の重要な役割があったものと考えられる。
ヤマトタケルの東征に随行する人物として、景行天皇は、まず吉備武彦と大伴武日連を任命している。吉備武彦は、王族との婚姻関係によって関係を深め、その軍事行動にも参加することで大和朝廷と連合関係を築いていた吉備一族の長であった。実際に、景行天皇の妃となった吉備氏の播磨稲日大娘は、ヤマトタケルを生み、吉備武彦の娘はヤマトタケルの妃となっている。
他方、大伴武日連は、朝廷の軍事を管掌していたと考えられている大伴氏の出身であったので、吉備武彦と大伴武日連は共に、軍事関係を担っていたと考えられる。
彼らと同様に、景行天皇は七拳脛を膳夫(料理人)として任命しているので、その文脈から考えても、七拳脛の担う膳夫(料理人)という役割は重要なものであり、単に料理を作るだけの役割以上のものがあったことがうかがえる。古代中国でも料理人が政権の中枢におり、宰相が料理組織を司っていたが、それと同じ事が、古代に日本においても見られたと推測できる。よって、七拳脛の先祖一族が軍事を担い、また七拳脛の子孫一族が神事を担ったように、その双方の役割を担った適任の人物だったのではないかと思われる。いずれにしても、景行天皇は膳夫(料理人)としての役割を軽んじてはおらず、むしろ重要な役割として息子のヤマトタケルの東征に随行させたのは間違いないだろう。
このような七拳脛の膳夫(料理人)としての最初の事績が存在するにも関わらず、七拳脛が磐鹿六雁命のように神格化されなかったのはなぜか。その理由は、割くという事績が、七拳脛の事績には含まれていなかったからではないかと私は考えている。あくまでも包丁で割くという行為そのものが重視され、それ故に七拳脛よりも磐鹿六雁命が神聖視され、それが割主烹従にへと発展していったのではないだろうか。
平安時代の包丁人
時代が下り平安時代になると、藤原山陰(824年-888年)という人物が包丁式の始祖として登場し、日本料理においては重要人物であると見なされている。藤原山陰は、孝光天皇の命によって、包丁式を定めた人物であるといくつかの包丁流派の秘伝書では説明されている。
藤原山陰の事績は、最初に包丁式を定めたというところにあるので、やはりここでも割くことが重要視されていたと理解出来る。そうした背景のもと、後に公家の四条家が、包丁式を家職として手がけ、四條流の包丁流派が生まれ現代においても、主要な包丁流派として知れられている。藤原山陰もやはり神格化されており、現在は京都の吉田神社内に山陰神社が設けられ、毎年、庖丁式が奉納され料理人から祀られている。
鎌倉・室町時代の包丁人
鎌倉時代から室町時代になると、貴族・公家に代わりに、新たに武家が台頭し力を持ち始める。このような背景を受けて、新しく武家独自の礼法あるいは、有職故実というものが生じるようになった。料理のおいても同様で、小笠原流、大草流、進士流、四條園流といった、新しい武家の包丁流派が生まれた。戦国時代の騒乱の中でいくつかのの流派は既に失われてしまったが、その幾つかは現代でも伝え続けられており、秘伝書や文献を通して、その時代の包丁式がどのように執り行われていたのかを理解する事が出来るようになっている。
こうした流派の包丁人は料理を実際にする料理人であったという訳ではない。包丁人は特別な祝宴か祭祀において、包丁式を披露したり、また饗膳の手配や指揮をとる事が主な役割であった。特に室町時代になると「
やがて各流派の包丁人は、単に料理を手配するということだけに留まらず、外交上の交渉事や政治的な駆け引きにも重要な役割を果たすようになっていった。これも、包丁人が、料理人よりも高い地位に置かれた理由のひとつであろう。
室町時代頃にその始まりがあるとされる、生間流という包丁流派があるが、この流派はもともと上級武家から始まった流派ではなかった。かつては包丁式を行なっておらず、鮟鱇の包丁式という見世物要素の強い包丁式のみが許されていたようである。しかし江戸時代になって、宮家の料理人となり、その間に四条家との確執を経て認められ、包丁式としての価値を高めて、包丁人として活動するのようになった流派である。だが宮家の料理人であったことから、生間流は包丁人というよりは、料理人の側に近い立場であったと言えよう。実際に有栖川ノ宮家の10代目当主であった威仁親王が1913年に嗣子なく薨去したための後継者がいなくなり断絶が確定する。これにより生間流そのものの存続も危ぶまれたが、京都の万亀楼という料亭が買い取って、現在も生間流派は続けられている。
日本料理の厨房組織への影響
このように日本料理の歴史を見ると、確かに包丁人が重要な役割を果たしていたことが分かる。それ故に、料理とは切り離して、別個に「包丁式」という、包丁技術を披露する儀式・儀礼が設けられていることを見ると、いかに日本料理においては割くことが重要なものとされているか理解できるはずである。
つまり「割主烹従」のルーツは、このような日本料理における、割くという行為を過度に重要視する、歴史的、文化的なバックグランドにこそ存在しているということが明らかになってくるに違いない。
しかし、人によっては、日本は海に囲まれた海産物の豊富な国であり、それにより必然的に料理においては割くことが重要視され、割主烹従はそれに伴って必然的に生まれたのではないかと主張するかもしれない。確かにそれも一理ある考え方ではあるだろうし、それも日本料理に含まれる重要な要素である事には間違いないだろう。しかし、世界のあらゆる国々で海に面した地域は沢山あり、海産物が豊かな国は何も日本だけに限定されてはいないということは見逃すべきではない。多くの国々や地域で、様々な新鮮な魚料理の方法が存在しているが、日本のような割くを重要視する精神や文化、厨房組織は他には存在していない。こうした違いを考えると、日本が海に囲まれている海産物が豊富な地域だからというような、外的な環境こそが「割主割烹従」を生んだのだと言うよりはむしろ、日本特有の割くことを神聖視する、歴史的あるいは文化的なバックグランドの存在こそが、「割主烹従」という考え方を生み出し、そのような料理を日本に定着させ、その故に必然的に「割くことを生かすための料理」として、鮮度の高い魚を生で食べる為の独自の食文化が生まれたのだとも考えられるのではないだろうか。
つまり、こうした背景があらるからこそ、磐谷六雁命は神となり、日本料理における特別な存在として現代においても祀られているのではないだろうか。磐谷六雁命が神として祀られてるようになった経緯を考えると、『高橋氏文』が後世にもたらした影響力は大きい。しかもそこにカツオを料理したという『日本書紀』にはないエピソードが挿入された事にこそ、その後の日本料理に与えた重要な核が含まれていると私は感じるのである。そしてそれこそが「割主烹従」のルーツであり、それが日本料理の厨房組織のありかたに、現代に至るまで大きく影響を及ぼし続けているように思われるのである。
「神」としての磐谷六雁命
磐谷六雁命が絵画に描かれる際には、ハマグリとカツオと共に描かれている。またそれに添えて覺賀鳥(ミザゴ鳥)が描かれる事もある。これは覺賀鳥の声を聞き、姿を見る為に海路によって淡水門を渡ることになったからである。磐谷六雁命のその後、つまり子孫となる高橋氏については、高橋朝臣の項で詳しく説明を行うが、その子孫代々が天皇の食事に関係した事は興味深い事である。
この高橋氏は、包丁人として、包丁流派を創始しなかった。実際には料理流派は四条流に基づいたものであったが、臣下の流派であることから、あまり表に出す事はなかったようである。また先祖の磐谷六雁命は大膳司で祀られていたが、時代の経過と共にその由来や、誰が祀られているかすら分からなくなっていたという時代もあった。こうしたなかで、磐谷六雁命が再考され、再び、強く神格化されていったのは20世紀初頭になってからである。
ことの発端は、ヒゲタ醤油の社長だった田中直太朗が醤油の歴史について調査を始め、大正2年に『醤油沿革史』という書籍を発行したことにある。その際に田中直太朗が、八百万の神の中に醤油の神様が存在するのかを調査を開始したところ、律令制度には定められた醤院(ひしおのつかさ)という役職と建物が定められており、そこで醤油の前身となる醤(ひしお)という調味料が作られていたことを知ったのである。さらに調査を進めると、この醤院では、高倍神というが祀られていることが分ったが、その高倍神こそが磐谷六雁命であることが明らかになった。磐谷六雁命がなぜ高倍神となったかについて、伴信友はもともと高倍は高瓮であったという説を述べている。醤院および造酒司ではその容器の瓮(かめ)は最も神聖なものとして常に祓い清め尊重されていた。醤院の座神である磐鹿六雁命を、高瓮神としたのも理由ある事で、その高瓮の文字がやがて簡単な高倍とへ変化したというのがその考えである。
ヒゲタ醤油は千葉県銚子の醤油メーカーであるが、その同県内の安房が、磐谷六雁命のエピソードの舞台であったという関連性から、さらに詳しい現地調査が続けられ、千葉県南房総市にある高家神社が、磐谷六雁命を祀る神社であることが明らかになったというのがその経緯である。
その後、ヒゲタ醤油社長の田中直太朗は『高倍神考 醤院座神』を著し、磐谷六雁命が醤油神でもあることについての情報を収集し、詳しい説明を行っている。
また大正12年には旧幕府諸藩料理指南、後宮内省大膳職包丁指南を務めた石井治兵衛が、『料理法大全』という、日本料理における重要な書籍を著しているが、そのなかでも始めの部分で早々に、磐谷六雁命とその謂れについて、『高橋氏文』を引用しながらその事績について言及している。また磐谷六雁命の子孫にあたる高橋氏一族の家系図も載せられており、どのようにこの高橋氏が日本料理を担ってきたのかが分かるようになっているが、その詳細は、高橋朝臣の項での説明に譲ることにしたい。
また昭和4年には料理研究会初代理事長の三宅孤軒が、『磐鹿六雁命御事績 : 料理界之祖神高家神社奉祀』という書籍を出版したが、磐谷六雁命について、まとめて詳しい情報が述べられている。この書籍は、『高橋氏文』の引用から、伴友信の注釈に関する解説、さらには千葉県南房総市にある高家神社が磐鹿六雁命を祀った神社である事を発見された過程の詳細が述べられており、貴重な資料となっている。
さらに興味深いのは、同書には広告として包丁会に属する全国の料亭が紹介されており、その他にも全国著名割烹店案内として、かなりの料亭が紹介されている。現在でも老舗として続けられている料亭もそのなかに含まれているのも興味深い。
最後に個人的な思い出を...
最後に個人的な磐鹿六雁命についての思い出を述べておきたい。私が初めて磐鹿六雁命を知ったのは、子供の頃に読んだ『包丁人味平』という漫画だった。主人公の塩見味平が、包丁試しをすることになり、上野不忍池にある包丁塚の前で勝負が行われるのだが、その包丁勝負の謂れのなかで料理の神様として磐鹿六雁命について説明されていたのが始めである。
『包丁人味平』という漫画は荒唐無稽なところがあって、それを面白がって読んでいたことを思い出す。そもそも塩見味平は、日本料理店の料亭の花板を務める塩見松造の息子なのだが、父親のような凄腕の料理人のつくる、上流階級の人々のための日本料理ではなく、誰もが美味しく食べれる大衆料理を目指して高校進学を辞めて街の洋食レストランのコックになる。そのレストランでの厨房で行う修行のなかで、「包丁試し」、愛知・熱田神宮境内での「点心礼勝負」、静岡・焼津の荒磯の板場での「荒磯勝負(かけ包丁)」 といった権威的な料理界のベテランとの勝負に味平は巻き込まれてゆく...。
話の展開はともかく、実はこの漫画、先に述べてきたような「包丁人が上で、料理人はその下である」のような、技術重視で味をおなざりにしてしまっている日本料理における問題点を、意識的にか、あるいは結果的にそうなってしまったのかは分からないが、間接的に浮き彫りにした作品となっているのである。
また『包丁人味平』というタイトルそのものにも、非常に皮肉なものを私は感じる。味平はコックであり、包丁人ではない。しかし、既存の料理世界における権威主義に対して、技術やしきたりではなく、味そのもので勝負を挑む事によって、既存の権威的な料理組織を打ち砕いてゆく内容にもなっているのである。こうして『包丁人味平』という漫画は結果的に、包丁人を頂点とする、日本料理としての有り方、日本料理の厨房組織、日本料理の割く事の技術重視の傾向に、疑問を投げかける内容も含んでいると私は考えているのである。
もしかすると、子供の時に接したこの『包丁人味平』という漫画を読んだ感想が、いまだに私のなかに存在し続けていて、日本料理における厨房組織や技術重視の割主烹従というスタイルに対して、疑問を私自身に投げ掛け続けているように思われるのである。
参考資料
『高橋氏文』群書類従. 第五輯 塙保己一 編
『高橋氏文考注』 伴信友
『新撰姓氏録考証』 栗田寛
『日本古代の国家と都城』 狩野久
『本朝月令』 高橋氏文 逸文
『政事要略』 高橋氏文 逸文
『年中行事秘抄』 高橋氏文 逸文
『醤油沿革史』 田中直太郎(金兆子)
『高倍神考 醤院座神』 田中直太郎
『磐鹿六雁命御事績 : 料理界之祖神高家神社奉祀』 三宅孤軒 編著